第001話
プロローグ
最強の化獣(ばけもの)クアンスティータ――
この想像を絶する超怪物を産み落とすのに必要な母体は七つ。
故に、母であるニナは七名必要だった。
同様に、父である怪物ファーブラ・フィクタも七つの魂が必要だった。
ファーブラ・フィクタは七つの魂に分かれて転生する。
一つは芦柄 吟侍(あしがら ぎんじ)という少年に……
残り六つの内、一つの魂が丹波 時銀(たんば じぎん)という少年に、二つの魂が大和 技陣(やまと ぎじん)という少年に、三つの魂が柳宮寺 仁義(りゅうぐうじ じんぎ)という少年へと受け継がれた。
……………………………………………
「丹波 時銀だな?」
舞い降りた天上使(てんじょうし)が告げる。
天上使とは地球圏で言えば天使のようなもの。
――が、その戦闘力は神をも凌駕すると言われている。
「天上使さんかい?」
時銀は質問に質問で返した。
「質問に答えろ、私は1級天上使メメタトロン。貴様を拘束しに来た」
「1級かぁ……天上使は0級から12級までの13レベルがあって1級と言えば、特別天上使の0級を別としたら最高位だねぇ……」
「不服か?」
「そうだねぇ……不服っていえば、不服だねぇ。一応、僕の中には神御(かみ)でさえ一対一では勝てない化獣(ばけもの)の一核、3番、ウィルウプス・アクルスを宿しているんだけど?神御のしもべに何が出来るっていうのかな?」
「だまれ、我々は忠誠に対する返礼として絶対服従と引き替えに神御をもしのぐ戦闘能力が与えられている。貴様にひけを取るつもりはない」
「はいはい、じゃあ、別の話をしよう。僕らを監視下に起きたいのは僕らが狙っているものが原因かい?」
「何のことだ?」
「働き蜂にはなにも知らせてないってことかな?じゃあ、ちょっとだけ教えてあげよう。神御や悪空魔が何故、化獣の中でも最後に出てくる13番、クアンスティータに対して過敏過ぎるくらいに反応するのかをさ」
「何を言っている?我々、聖なる者は貴様ら化獣に関して言えば共通して危険意識を持っている。3番を宿す貴様とて同様だ」
「違うね。明らかにクアンスティータだけを特別視している。……確かにクアンスティータは最強と言われている化獣だ。特別視してもおかしくはない。でも神御や悪空魔の反応は特別視というよりはむしろ恐れているんだ。ある三つの名前が出てくる事をね」
「訳のわからぬことを言って誤魔化すつもりか。我々は……う、動けん……」
メメタトロンは自分の動きが封じられていることに気付いた。
虹色の光が絡みついて、彼を束縛している。
「あぁ、今頃解った?君の動きはとっくに止めている。殺そうと思えばいつでも殺せるよ。だけど、そんなことに意味はない。ならどうするか?事情を知らないでバカ正直に行動している君に神御の考えを少し教えて反応を見てみよう。そんな気持ちになったのさ」
「ふ、ふざける……」
「【な】といいたいんだろうけど、まぁ、聞きなよ。クアンスティータは神話の時代、レインミリーという心優しい少女だったんだよ。だけど、神と悪魔の頂点に立とうとする浅ましい考えの持ち主達によって、死より怖い目にあわされた。それを不憫に思った両親、ニナとファーブラ・フィクタはクアンスティータとして産まれなおさせようとした。神や悪魔に邪魔されてしまったけどね」
「悪魔はともかく、神には考えがあったのだ」
「盲信ってやつか、哀れだねぇ。確かに考えがあったんだよ。神にも悪魔にも。彼らは単純に怖かったのさ。転生に使われた三つの名前がね」
「神は正しいのだ」
「うるさいな。黙って聞けよ。クアンスティータは17の側体は別として7つの本体を持っている。第一本体・セレークトゥース、第二本体・ルーミス、第三本体・レクアーレ、第四本体・ミールクラーム、そして、第五、第六、第七本体だ。ぼかして言ったけど、解るよね?第四本体までなら神も悪魔も許した。特に、第三、第四本体の能力は魅力的だったからねぇ。だけど、残り三つこそ神や悪魔も震え上がった。第五本体・リステミュウム、第六本体・レアク・デ、第七本体・テレメ・デ……この三つこそ、解き放ってはならないブランドだったからだ。ファーブラ・フィクタが残した言葉、【クアンスティータさえ産まれていれば、お前達などひとたまりも無かったのに】を現実のものに変える力そのものだったからだよ」
「神御は何者をも恐れぬ」
「じゃあ、帰ったら聞いてみなよ、リステミュウム、レアク・デ、テレメ・デの名前を出したとたんに君は消されるよ。怖くてたまらないんだよ。その三つの名前はクアンスティータという名前でオブラートに包んでしまっておきたいんだよ。クアンスティータという包み紙がとれてしまうと中身が出てきてしまうからね。表に出る前にそっと隠して置きたいんだよ」
「神御を愚弄するな」
「神御どころかその上でふんぞり返っている連中もブルブルと震えているよ」
「許さぬ、許さぬぞ」
メメタトロンは憤怒の表情を浮かべる。
時銀の言葉は逆鱗に触れたのだ。
信じていた事を根底から覆す、許されざる言葉だったからだ。
今すぐ向かっていって八つ裂きどころか万裂き、億裂きにしても飽き足らない気持ちに包まれた。
確かに、ただの人間の時銀に神御の最高戦力の自分が行くのに疑問を持たないでもない。
確かに神御の力を上回ると言われている3番の化獣ウィルウプス・アクルスを宿しているとは言え、宿主となっている時銀はただの人間だ。
天上使であるメメタトロンが飛びかかれば、一瞬にして消し去る事だって不可能じゃない。
怪物、ファーブラ・フィクタの生まれ変わりだろうとただの人間なのだ。
が、現実として、完全にメメタトロンは動きを封じ込まれてしまっている。
この上ない屈辱だった。
血の涙が頬を伝う。
「もっと、幸運を喜んでくれても良いんじゃない?これが、技陣君や親方だったら命が無かったかも知れないんだよ。僕だから生きて帰すって言ってるのに」
「生き恥はさらさぬ、殺せ」
「おいおい、天上使の癖に自殺はいけないな。聖なる者としては失格じゃないの?」
「ぬうぉぉぉぉぉぉっ」
「いくら叫んでも君じゃ、その呪縛は解けないよ。それより、情報を持ち帰る方が、忠義を示せるんじゃない?」
「くっ………」
「僕はオープンだから、知っていたんだろうけど、三人の中じゃ、僕が最強というのは間違った解釈だよ。僕は最弱なんだ。ファーブラ・フィクタの魂は芦柄 吟侍と同じく一つしか持っていない。化獣も一核だけ」
「な、なんだと?」
「技陣君は二核、化獣を宿しているよ、5番、ルルボアと11番レーヌプス。ファーブラ・フィクタの魂も二つ持っているし。――でも技陣君も最強じゃない。最強は三つの魂を持っている親方、柳宮寺 仁義さんさ」
「ば、バカな、ファーブラ・フィクタの魂を多く持っているくらいで……」
「ほんと、何も知らないんだね。ファーブラ・フィクタとニナの子供である化獣は13核って言われているけど、用意された核の数は168。その内、化獣に使われたのが、1番、ティアグラから12番、クアースリータまでが1核ずつと13番クアンスティータに使われた96核のあわせて108核。つまり、60核分、余っているんだよ。仁義さんはその内、半分を所有してるんだよ。解る?格が違うよ、格が」
「なっ……」
「もう一度言うよ。僕らを捕らえるには神や悪魔のトップが総がかりで来たってものたりないんだよ。出直して来な」
1級天上使メメタトロンは震えが止まらなかった。
自分の知覚出来る範囲を超えた何かが蠢いているのを感じたからだ。
時銀は神のトップとも言った。
トップとは恐らく真神(深神/しんじん)を指す。
メメタトロンにとっては謁見すら恐れ多い程の上の存在だ。
それ程の存在すら持て余すかも知れない者と自分が関わろうとした、挑もうとしたと考えると恐ろしくなってきたのだ。
「おぉ……神御よ、神御よ……」
メメタトロンは神に祈った。
「……さすがの僕らだってテレメ・デだけは特に怖い。だから、仲間総出で最高の歌い手を集めてから動くつもりだ。眠らせる事が出来る歌は多い方が良いからね。万全に万全を来すつもりだよ。だからほっといてくれないかな?」
「恐ろしい……恐ろしい……」
メメタトロンには既に戦意は無かった。
呆然と立ちつくす天上使を尻目に時銀は去っていった。
メメタトロンは時銀の言うとおり、マシだった。
技陣に挑んだ天上使達は跡形も無く消し飛ばされてしまっていたからだ。
それこそ、交渉の余地など全くなく。
仁義に挑もうとした天上使達も近づく前に技陣の手によって始末されていた。
仁義一派は基本的に仁義を中心として動いているが、仁義も№2の技陣も群れるのは嫌っていた。
それ故、一派を指揮していたのは№3の時銀だった。
そのため、神御は時銀をリーダーと勘違いしていたのだ。
歌姫集めも時銀の指示だ。
だが、この物語の主役は彼ではない。
柳宮寺 仁義という少年である。
第一章 仁義と華芽菜とバトル・チア
「ふぁ~あ……寝みっ……」
柳宮寺 仁義は大あくびをする。
ここのところ、退屈だからだ。
勝手に舎弟になった丹波 時銀という男が親方、親方とうるさいので、逃げて来たのだ。
元々、群れるのは好きじゃない。
勝手気ままに生きるのが仁義の生き方だ。
時銀が言うには大きな宿命とやらがあるらしいがそんなことは知ったことではない。
俺は好きな様に生きるだけ……お山の大将に興味はない。
そう思って放っておいたが、仁義の舎弟が勝手に増えてくるので鬱陶しく感じていた。
自分の事を知らない所に行こうと思って行き着いた場所がこの星だった。
とりあえず、する事が思いつかないので辺りをブラッとしていたら眠くなったのだ。
仁義はそのまま仮眠を取った。
バトル・チア用コートのど真ん中で。
「すみません、起きて下さい。ねぇ、ちょっと起きてってば」
「やめなよ、華芽菜(かめな)。ちょっと怖い人かもよ?」
「何、言ってんのよ鈴子(すずこ)、これじゃ練習にならないでしょ。コートのど真ん中で高いびきとは良い度胸してると思うけど、人の迷惑も考えて欲しいもんだわ」
竜乃宮 華芽菜(りゅうのみや かめな)とその友人、榊 鈴子(さかき すずこ)はこの星のメジャー競技、バトル・チアの練習をしにコートに寄ったのだ。
そこに仁義が寝ていたのだ。
「なんだよ、五月蠅ぇな、気持ちよく寝てるって時に」
「場所を考えてよ、場所を。ここは、バトル・チア専用コートよ」
「バトル・チア?何だそりゃ?」
「あんた、宇宙人?この星でバトル・チア以上に有名なスポーツなんて無いわよ」
「まぁ、別の星から来たってのは否定しねぇよ。そうだな、睡眠の邪魔をしたんだ、俺にそのバトル・チアってのを見せてみろよ」
「何様なの、あんたは」
「俺様だ」
「知らないわよ、あんたなんか」
「ちょっと、やめなよ華芽菜、ごめんなさい、この子ちょっと気が強くて、男の人が苦手で」
「違うわよ。男なんて最っ低の生き物だって思っているだけよ。バカでスケベでどうしようもなくアホで」
「ふーん、だがよぉ、何か事を為すのは大概あんたの嫌う、そのバカやアホだぜ。良い子ちゃんな奴は大抵何も出来ない。あんたはそんなつまんねぇ奴の方が好みなのか?」
「な、何言ってんのよ、人間は清く正しく美しくって言うのが理想なのよ。ルールすら守れないバカはどうしようもないのよ」
「ルールってのは誰が決めたんだ?そのルールってのに縛られて生きなきゃなんねぇのか人間ってのは?」
「あったりまえでしょ、何言ってんの」
「ふーん、あんたとはとことん、気が合いそうもないな。気に入った。しばらくあんたを観察してみよう。何かあるかも知れん」
「な、何言ってんのよ、私をストーカーするつもり?」
「ストーカー?」
「私につきまとっていやらしい事をしたりする奴の事よ」
「別にお前の身体になんて全く興味はねえよ。お前より、良い女なら腐る程、言い寄ってきてたからな」
「まぁ嫌らしい」
「や、やめなよ、華芽菜ぁ……やっぱり怖い人だよ」
「怖い?」
「ご、ごめんなさい。そんなつもりじゃ。気を悪くしないで。私達急いでいるので、これで失礼します。行こ、華芽菜」
「ちょっと、鈴子、私はこいつにもっと言ってやりたいのよ」
「良いから、華芽菜」
鈴子は華芽菜を引っ張って、その場を立ち去った。
残された仁義は……
「バトル・チアか……まずは、そいつから見てみるか……」
この星に興味を持った。
仁義はとりあえず、このバトル・チアというスポーツを調べる事にした。
――バトル・チア……
このスポーツは格闘応援競技というものだった。
ルールは複雑になっているが、簡単に言ってしまえば基本的に応援対象がいて、その応援対象を勝たせるために戦う競技らしい。
応援対象が最後まで立っていた方のバトル・チアリーダーの方が勝ちというルールが原則だ。
複雑だというのはこの試合形式が複雑に変化する事にある。
例えば、応援対象にスポットライトを当てれば、応援対象がただ、立っていたら、最後まで倒れずに立っていた方が勝利となるが、応援対象がテニスをしていたらバトル・チアリーダーは応援対象にテニスで勝たせれば勝利となる。
応援対象同士がテニスボールを打ち合いしていて、バトル・チアリーダーがテニスボールに打撃などを入れて、ボールの動きに変化させてもルール違反ではなく、応援対象に得点が入る。
とにかく、応援対象を勝たせる事がバトル・チアリーダーの勝利になるのだ。
応援対象が何をするかによってもルールが複雑に変わって来るのがこの競技の特徴だ。
もちろん、応援する側、バトル・チアリーダーにスポットを当ててもルールが複雑に変化する。
例えば、基本的に応援対象が1名、バトル・チアリーダーが1名で1チームとなって相手チームと戦うのがオーソドックスルールだが、チアリーダーや応援対象の人数が変わったりもする。
他にも1チーム対1チームではなく3チーム以上での乱戦というバトルスタイルももちろん存在するのだ。
どのスポーツをも含むという段階で、オールマイティーな競技として、この星では最もメジャーなスポーツとして認識されているのだ。
そして、竜乃宮 華芽菜はこの地区では敵無しの選手だと言うことも解った。
仁義はそこで思いつく。
気の合わない華芽菜と行動を共にしても衝突するだけだ。
ならば、華芽菜に勝てるように無名の選手を育てて見るのも面白そうだと。
仁義は退屈しのぎの良い遊びを知ったと喜んだのだった。
となれば、協力する選手を探さなくてはならない。
その選手が弱ければ弱いほど、気の強い華芽菜のプライドは傷つくだろう。
それは、どんな気持ちだろうかと楽しみに思えてくる。
――仁義という人間は正義の味方には決してなれない。
彼の中での正義感というものが偏っているからだ。
正義の味方がしてはならないことも平気でするからだ。
なれたとしてもダークヒーローが良いところだろう。
彼が芦柄 吟侍と違う点を例に挙げてみよう。
例えば、子供の頃のイジメという問題が出たとする。
吟侍の場合はイジメの原因を探り、その原因を解消させてイジメの原因を取り払うという方法をとるだろう。
仁義の場合はどうだろう……
イジメの原因を探す……いや、違う。
イジメの首謀者を懲らしめる……これも少し違う。
では、何だろう――
彼は、イジメの首謀者はもちろん、その首謀者の尻馬に乗って、イジメを煽った小悪党にも目を向ける。
子供の頃の体力差というものはあまりない。
つまり、首謀者が一人、ターゲットとなってしまった被害者を嫌っていてもそれは喧嘩にはなってもイジメとはならない。
イジメにはその行為を煽る裏方が存在する。
首謀者だけでなく、裏方も交えた集団となり、一人または、少人数をイジメという形で貶めるのだ。
首謀者は裏方が居ることにより、エスカレートしていき、取り返しのつかない結果を招いたりする。
そして、問題が大きくなると、裏方は責任を首謀者になすりつけ、自分達は気配を消してほとぼりが冷めるのを待つ。
仁義はその裏方が許せないのだ。
安全な位置から他人を傷つけ、気まずくなったら、すぐに責任逃れをする。
それが、小悪党、イジメの裏方共だ。
事の本質を見抜く、仁義はこのやり方に嫌悪感を持っているため、裏方達にも凄まじい仕置きをする。
赤の他人から見れば、それがやり過ぎと映り、ヒーローとして認められない理由でもある。
仁義はそんな目で見る他人の事も何も見えてないクズだと軽蔑した目で見ている。
それが、正義の味方になれない最大の理由だった。
仁義を慕ってやってくるものは多い。
だが、集団で、少数を攻めるというやり口が嫌いな仁義は群れるのを嫌がる。
だから、彼はいつも孤独だった。
それは前世である怪物ファーブラ・フィクタの性質を色濃く受け継いだという事でもある。
ファーブラ・フィクタもまた、そんな人間の弱さを嫌っていたからだ。
反面、レインミリーの様な心優しい存在もいるとどこかで信じている。
だから、全てを潰そうとはしなかった。
ゴミの様に嫌っている人間達に対してどこかで希望を持っていたのだ。
だから、嫌いな人間達に関わろうとちょっかいをかけたくなっている。
仲間としてではなく、敵として。
そこが人間に対する好意と悪意のジレンマを持つ仁義の行動理由だった。
仁義にとってはバトル・チアというスポーツなどどうでも良いのだ。
ただ、人間の反応を見れればそれで良い。
理由は後付けに過ぎない。
仁義はルールを覚えた後で、バトル・チアのクラブチームを見て回った。
仁義の運動神経からみたら、どいつもこいつもドングリの背比べ状態だったが、もっと低いレベルで見ると、確かに実力の上下はあるように見えた。
その上で、強いと言われる選手が何故、強いか、弱いと言われる選手が何故、弱いかを探っていった。
見ていった結果、教え方次第で、弱い選手も十分、強い選手に対抗出来る力を手にする事が出来るという、事が解った。
他人のコーチングを見ているといかに選手にコツを掴ませ、勝たせるかでそのコーチとしての資質が問われることも解った。
自分の無能さを棚に上げて選手に対して怒鳴り散らすダメコーチも居れば、選手の才能を上手く引き出して上達させているコーチも居る。
後者が名コーチと呼ばれる事は仁義にも解った。
能力を与える訳でもなく、他人の能力を引き出して、勝たせる――
それは仁義がいかに強くても、上手く、選手を鍛えられなければ、指一本使わずに消し飛ばせる人間がコーチングした選手に負ける事もある――。
仁義の勝利が絶対的じゃない。
そこが、仁義には楽しく思えた。
勝つか負けるかはその選手の成長次第というのがギャンブル性もあって、楽しく思えた。
ならば、才能の欠片もない選手よりは、才能は眠っているが、それが、上手く引き出せていない選手を見つけて、その選手を鍛える方が楽しいと理解した。
彼は、念入りに選手を見て回ったが、その期待に応える選手は見つからなかった。
が、選手以外に三人、興味深い人間を見つけた。
行動力が早い彼は早速アプローチをしかけるのだった。
「おい、お前……」
「あ、は、はい、何でしょうか?」
「沢宮 理路(さわみや りろ)16才だな?」
「あ、あの…あなたは?」
「答えろ、沢宮 理路だな?」
「は、はい……」
仁義が見つけた一人目の人材、沢宮 理路は華芽菜達の学校のライバル校、上珠(うえたま)女学院のバトル・チア部員だった。
部員とは言ってもチーム戦が多い、バトル・チアにおいてはチームワークも大切となる。
部内で浮いた存在である彼女はチームメイトと打ち解ける事が出来ず、イジメを受けていた。
部内で浮いていたのは並外れて平衡感覚が優れていたため、他の選手の下手さが目立ってしまった。
それをやっかんだ他の選手が理路とのチームプレイを拒否したのだ。
拒否した上で、不器用な者達なりに、チームプレイを強化していったので、理路だけが入らない人材として、取り残されてしまったのだ。
才能が有りすぎるが故にはじかれてしまったという不幸な例である。
努力していけば、その内、日の目を見ることもあると日々隠れて努力をしていたが、コーチがイジメをしているチームメイト達とグルだという事が先日わかり絶望して、自殺を図ろうとしていたのだ。
首を吊る場所を探して、うろうろしていたら、仁義が現れ、慌てたという状況だった。
「お前、死ぬつもりだったろ?」
「えっ……いえ、そんな……」
「お前、つまらん他人の為に死を選ぶなんてバカな真似をするつもりなら、俺が殺してやるよ。たっぷり苦しんでくたばるんだな」
「い、痛いのは、……」
嫌ですと言いたかったが仁義の思わなぬ迫力に言いよどんだ。
「悔しくないのか?」
「い、いえ……そんな……」
「はっきりしろっ!」
「ど、どならないで……」
「どうなんだ?」
「で、でも、バトル・チアはチームワークのスポーツだし……」
「バカかてめぇは?」
「え?」
「年がら年中連んでる奴らが強くなる訳ねぇだろうが!個々に自分を高めていってたまに力を合わせるから価値があんだよ。てめぇらのチームは傷をなめ合っているだけだ。本物には絶対に勝てねぇ」
「あ、あの……あなたは?」
「勝ちたきゃ、俺と来い、こんな保身だらけの腐れチームに居るよりゃマシなチームを作ってやる。てめぇはそこでキャプテンをやれ」
「え?」
「良いから来りゃいいんだよ。とっとと、ここ辞めて俺の所に来い。早くしろ」
「は、はいっ」
まくし立てた仁義の迫力に圧されて、理路はその足で、学校を辞めた。
退学届けと遺書を間違えて出した時には死にたくなるくらい赤面ものだったが、不思議と仁義と一緒に行けば何とかなるかも知れないと思えたから旅の恥はかき捨て気分で辞める事が出来た。
一緒に行けば、明るい未来が待っている。
そんな気持ちで仁義の元に戻った。
「あ、あの辞めて来ました」
何かを期待したキラキラとした目だ。
「そうか、じゃあ、俺は次の奴をスカウトに行くからお前は練習場を確保しろ」
仁義はそう告げた。
「え?……練習場って?」
理路は仁義はどこかの有名クラブの監督か何かで、彼女はスカウトされたと思っていたのだ。
だが、仁義はルールを覚えたばかりだ。
当然、クラブチームなど、持っていない。
有望だと思える選手をかき集めてチームを1から作るつもりなので当然、何もない。
「バトル・チア練習場だよ。そのくらい確保しとけ。俺はお前のチームメイトって奴を探すのに忙しい」
「えぇ……?」
理路は途方に暮れた。
仁義は自分の願いを叶えてくれるために現れた王子様ではなく、ただの滅茶苦茶な人だと思ったからだ。
結果、バトル・チアに最低限必要人数である三人を集めて来たが、バトル・チア経験者は理路一人だけだった。
一人は素行不良で退学になった杉浦 可奈(すぎうら かな)で、女の子相手なのに無理矢理喧嘩をふっかけて、完膚無きまで叩きのめし、命乞いをさせて、助けてやる代わりにバトル・チアをやれと脅してきたらしい。
元々、かなりやさぐれたヤンキーだったと聞いたのに、現れたのは仁義に対して、異常に怯える気の弱そうな少女だった。
もう一人はホームレスの少女。
当然、学校にも行っていないので、バトル・チアの経験もない。
三食昼寝付きだからと勧誘してきたらしい。
驚くべきはこの少女には名前が無かったという事だ。
そこまでの環境でもあるにもかかわらず、仁義は
「お前の名前は今日から【ぽち子】だ。ついてこい」
との一言で連れてきたらしい。
無茶苦茶だ、この人は……。
理路はそう思った。
更にびっくりしたのは通りかかった敵無しの女王、竜乃宮 華芽菜に向かって
「おう、かめ子か、今、最強チームを作っててめぇのチームをぶっ潰すから覚悟しとけよ」
とのたまわった事だった。
また、ルールは解ったけど、実際に見てみないと何の事だか解らないから、実戦して見せろと説明を理路に求めてきた。
教えるどころか教わる立場だったのだ。
ダメだ、この人――
そう思って、諦めていたが、いざ、練習に入ると元々才能のあった理路は仁義のコーチングの上手さに舌を巻いた。
基礎すらよく解っていなかったとはまるで思えないような応用力。
これが、ルールを把握したばかりの人間の発想かと思える程のものだった。
現に、全くの素人だった、可奈とぽち子の上達ぶりは才能を持っている理路でさえ脅威を覚える程の伸び率だった。
そう――
仁義は元々、戦いの超天才でもある。
戦い方の応用で考えれば、スポーツであるバトル・チアであっても驚くべき攻撃を思いつく事だって出来るのだ。
今までのバトル・チアの常識では計り知れないバトルセンスが仁義からは感じられた。
仁義にとってみれば、ルールを決められているだけの戦いと同じで、どうにでも戦法は思いつくのだ。
そして、一月後には、バトル・チアの大会に参加していた。
当然、無名の仁義率いるトリッキーズは最下級ランクからの勝ち残り戦からの出場だが、驚くべき戦績で勝ち残っていった。
最下級リーグに強いチームが出てきたという情報が広まり、その上のリーグに勝ち抜いたトリッキーズを見に華芽菜のチームもやってきた。
「この子達がトリッキーズ……なんて無茶苦茶な戦い方をするチームなの……」
華芽菜の一言はトリッキーズの戦い方を示していた。
例えば、ペア競技、サンドバッグフォールという競技がある。
各チーム二人ずつ出場し、先に相手陣地にある三つの内、二つのサンドバッグを落とせば勝ちというバトル・チアの競技の一つだ。
これは自分の陣地の離れた所に三つあるサンドバッグを守りつつ、敵の陣地にあるサンドバッグを落とすという競技であり、オフェンス、ディフェンス各一人ずついる。
オフェンスは攻撃しか出来ないし、ディフェンスは守備しか出来ない。
オフェンスは味方のディフェンスがサンドバッグを守っている間に、敵のディフェンスの防御をかいくぐり、二つサンドバッグを落とすというものだ。
仁義が指示したのは自陣のサンドバッグの一つを自ら落とすというものだった。
ルールには確かに、自陣のサンドバッグを落としてはならないとは書いていない。
これは、一見不利に見えるかも知れない。
だが、これは、味方のディフェンスが守る範囲を狭めたので、敵のオフェンスを防御しやすくしたというものだった。
当然、自分でサンドバッグを落としても敵にも味方にも得点は入らないが、体力を維持したまま防御出来るという利点がある。
オフェンスの方も微妙な位置で停止して、敵チームのディフェンスに揺さぶりをかけた。
敵のオフェンスが思わぬ防御に合い、ディフェンスはいつ攻撃を仕掛けてくるか解らないという揺さぶりを受けていた。
必要以上に精神力と体力を削りとって、後半に一気に攻める。
それまでは、動くふりをして、じっくり力をためるというやり方で勝利している。
こういうルールの穴をつくやり方で勝ち進んでいるのだ。
ルールに記されていない部分をついて攻めてくるから、敵のチームとしては対処の取りようがない。
戦いにくいというイメージに加え、【トリッキーズ】という名前が何か変な動きをしてくるのではないかという警戒心を与え、正攻法での攻撃が逆にフェイントとして、機能していた。
「こんなの邪道よ。実力とは認められないわ」
華芽菜がつぶやく。
それを監督席から聞いていた仁義は
「よう、かめ子。そいつはどうかな?自分の力を過信してるとやられるぜ」
といった。
「こんなの私達には通用しない」
「バカかお前は?」
「何ですって?」
「てめぇが偵察に来ていると解っていて、手の内さらすバカが何処にいる?てめぇと当たる時はまた、別の手で攻めるんだよ」
「どんな手を使ったって……」
「勝つ自信あんのか?てめぇの知らない何かが飛び込んで来ても」
「ムカツク男ね、あんた」
「ムカツクのはお互い様だ。スタープレーヤー様は俺の兵隊を打ち負かして無事、ヒーローと呼ばれるでしょうか?」
「性格悪いわね、あんた。ヒーローの器じゃないわ」
「俺はヒーローが嫌いでね。どちらかというとヒーローを小馬鹿にする道化師ってのが性に合っているな」
「帰る」
「おう、帰れ帰れ!大事な所見逃してチャンスをふいにしな」
「あぁ、言えばこういう……」
「ちったぁあがいて、俺を悔しがらせろよ。じゃねぇとつまらねぇだろうが」
「何がしたいのよ、あんた?」
「負けてみたいんだよ。思いっきりな」
「はぁ?」
「わかんねぇか?わかんねぇよな……力を持ちすぎた奴の憂鬱ってやつは……」
「あんたが、その力を持ちすぎた奴って事?」
「さあなっ、とりあえず、楽しませろよって事だよ。もっとあがけ!シーソーゲームになんねぇとつまんねぇだろうが」
「………」
華芽菜は仁義の言いたい事が解らなかった。
が、その悲しそうな瞳からこいつも何かあるんじゃないか……
隠している辛さがあるんじゃないか……
そう思ったら……
「……負けないからね」
「帰るのか?」
「……そうよ、でも逃げ帰るんじゃない。あんたに勝つために出来る事をしにいくのよ」
「見なくていいのか、試合?」
「良いわよ、見なくても。見ても違う事されるなら見ている意味は無い。かえって邪魔な情報が入るだけよ。何かやってくると解っただけでも収穫よ」
「ははっ、正解だよ。その判断は。やっぱ、お前は俺がライバルと認めただけはある。応援してるぜ、是非、俺に勝ってくれ」
「変なやつ」
「褒め言葉として受け取っておくぜ」
「好きにして」
華芽菜はそのまま特訓に向かった。
このままだとトリッキーズに負けると悟ったからだ。
敵の強さを把握するというのも強さの上で重要な要素だ。
華芽菜は特訓で自身の身体をいじめぬいた。
が、無理がたたったのか練習中、怪我を負ってしまった。
そして、トリッキーズと当たる前にドクターストップがかかってしまった。
戦えなかったとして悔し涙を流す華芽菜。
そこへ仁義がやってきた。
「よう、かめ子」
「何よ、笑いに来たの?」
「いや、礼を言いに来た。サンキューかめ子、楽しかったぜ、この余暇は。人間の言う、青春ってやつを擬似的にでも味わえた。真っ直ぐに俺に立ち向かって来たお前の気持ち、俺にはきっちり伝わったぜ。参考にさせてもらう。良いアイディアが浮かんだ」
「何よ、それ」
「最高の娯楽さ。バトル・チア、なかなか面白い競技だ。だが、俺には小さすぎる。俺用の娯楽をこれから立ち上げる。――バトル・チアから名前の一部をもらうぞ。プロフェッショナル・バトル・ストロンゲスト――略してプロ・バトだ。プロの戦闘最強者を決めるスポーツだ。未開の世界の強者を集めて、最強を決める大会だ。ワクワクするねぇ」
「何なのよ、一体、それはぁ~」
「喜べ、お前はそのスポーツの可能性を示した。お前も発案者の一人だ」
「訳わかんないってばぁ」
「十年、いや、一年で良い。待ってろ。環境を整えてお前にも見せてやる。ひ弱なお前でも安全に見れる環境を作ってくる」
「もっと具体的に説明……」
しなさいよ――と言いかけた華芽菜はギョッとする。
仁義の背後に数え切れないくらいの影が現れた。
その影はどれもこれもただ者じゃない雰囲気を醸し出している。
「親方ぁ、なんなんスか、こいつは?」
「てんで、弱そうじゃないですか?」
「こいつをぶっ殺せばいいんですかぃ?」
口々に悪態をつく影。
すると、仁義は――
「黙れ、こいつは俺のライバルだ。悪く言う事は許さん」
と言った。
「へい、すいやせん」
「了解しました」
「申し訳ありません」
影が詫びを入れる。
その事からも影は仁義に従っていることが解った。
「何者なの、あなた?」
華芽菜はつぶやいた。
「言ったろ、お前のライバルさ。それ以上でも以下でもねぇ。俺はプロ・バトを盛り上げる。お前はバト・チアを盛り上げろ。勝負だ」
「勝負って……」
「二年だ。立ち上げに一年、第一回大会に一年やってみた後、お前に俺のプロ・バトを見せに来る。お前はその間にバトル・チアを盛り上げておけ、俺の見た所、バトル・チアの才能を持っている奴は他にもいる。そいつらかき集めて今よりレベルを上げておけ。面白い大会になった方が勝ちだ、良いな」
「そんな勝手に……」
「いくぞ、お前らぁ」
一方的に話が進み、ついて行けない華芽菜を尻目に、やる気に満ちた仁義。
「うぃす」
「おぉっ」
「いきやしょう親方ぁ」
それに呼応する影達。
今まで、無気力だった仁義がその気になり、配下の志気も上がる。
自分勝手に人と関わり、自分勝手に納得して出て行った。
第二章 プロフェッショナル・バトル・ストロンゲスト
華芽菜と分かれてからの仁義だが、持ち前の行動力の早さから、幹部の技陣と時銀を招集、三班に分かれて行動するための支持を出した。
目指すは虚無六界(きょむろっかい)と呼ばれる世界だった。
虚無六界――
神が支配するとされる三つの世界、天界、楽園界、仙界、
悪魔が支配するとされる三つの世界、魔界、幽界、冥界、
神か悪魔が支配するとされる一つの世界、人間界(限界)、
それに化獣が支配するとされる二十七の世界(一番のティアグラが支配する世界、七番のルフォスが支配する世界、十二番のクアースリータが支配する世界(ロストネットワールド)、十三番のクアンスティータが支配する二十四の世界)を足して、三十四の世界が全ての世界とされている。
それらを総じて三四界(さんじゅうよんかい)と呼んでいる。
が、実際にはその三四界に含まれない六つの世界が存在する。
それが、虚無六界だった。
虚無六界はクアースリータのロストネットワールドに取り込まれなかった数少ない強者の世界でもある。
虚無六界の大きな特徴――
それは、三四界では深く浸透している十三番の化獣クアンスティータへの恐怖が無いという事でもある。
そう――虚無六界の住民はクアンスティータを恐れない。
それは、まだ見ぬ強者が居るかも知れないという事でもある。
仁義達はこの虚無六界へと渡り、クアンスティータの最強伝説を伝え、異論が有れば、最強で有ることを示せと言って回ることにしたのだ。
各、虚無六界で最強を決め、それで、六界の代表同士で最強を決め、それが、クアンスティータへの挑戦権を得るという交渉をして回る事にしたのだ。
虚無六界は虚界三界(きょかいさんかい)と呼ばれる三つの虚界と無界三界(むかいさんかい)と呼ばれる三つの無界を足した六つの世界をさす。
虚界三界は虚絶界(きょぜつかい)、虚湧界(きょゆうかい)、虚裏界(きょりかい)の三つ。
無界三界は無真界(むしんかい)、無全界(むぜんかい)、無想界(むそうかい)の三つだ。
この六つの世界を更に地域別に四つずつのリーグを作り合計24リーグ設立する事にっした。
24リーグにしたのはクアンスティータが本体7つ、側体17の合計24の身体を持つため、それに合わせたのだ。
各リーグはその地域の№1を決めてから、4リーグ総当たり戦で、世界の№1を決めて、更に六つの世界での統一№1を決めるという大会だった。
選手はストロンゲストと呼ばれる強者達で、相手を消滅させてはならない。
それさえ守れば、例え殺しても良いというルールだ。
虚無六界にとって死は大した意味がないからだ。
身体さえ残って居れば、死からの生還は容易い事が解っている。
死の概念が三四界とは違っているのだ。
バトル・チアから派生した、プロ・バトのルールは様々な形式がある。
まず、観客の安全を考えて、戦う者達の影響が観客に影響しない環境を整える必要があった。
そのため超強固なバトルフィールドの確保が必要となる。
それは元々、強者達の戦いにも耐えうる強度を誇っている虚無六界でのバトルが望ましかった。
参加者のスカウトの傍ら、仁義達はこのバトルフィールドの確保にも力を入れた。
もちろん、これらを実現するには、多くの反対意見、面白く思わない者の妨害も数多くあった。
それを納得させるためにも仁義達自身が虚無六界の強者達と戦い、力を示していった。
そして、僅か、半年である程度、話をまとめるにまで至った。
予定より、早く出来るのは仁義達の仕事の速さのたまものでもある。
そして、プロ・バトの総責任者は仁義一派では101番目の実力者ラスティー・プロログが就任することになった。
大会開催の条件が仁義一派の実力者上位100名は虚無六界のどこかのリーグのどこかのチームに入り、プロ・バトへの強制参加でもあるからだ。
仁義も技陣も時銀も当然、プロ・バトへの参加が義務づけられたという事でもある。
仁義としてもこんなに面白い大会に参加できるのなら、総責任者として、事務作業などをしているよりは断然良いと思っている。
もちろん、100名はそれぞれ別のチームに入っている。
仁義達への下位メンバーの下克上もありだ。
当然の様に、仁義、技陣、時銀はそれぞれのリーグで頭角を現し始めていた。
――が、それでも、容易には勝てない程の強者が虚無六界にはうじゃうじゃ居た。
仁義達はそのままでは勝てないと思って修行などや、肉体改造なども頻繁に行っていった。
プロ・バトでの戦いが自分達を信じられないくらいのレベルに引き上げてくれる。
そんな戦いの日々だった。
そして、第一回大会が開かれ、仁義達も善戦したが、仁義達のチームはリーグ代表止まり、世界戦にも六回統一戦にも出られなかった。
技陣や時銀のチームは予選すら突破出来ていない。
これが、余りにも高い虚無六界のレベルだった。
優勝チームはクアンスティータとのバトルの権利を得たが、肝心のクアンスティータはまだ産まれてもいない。
こうやって、毎年№1を決めてクアンスティータが年頃になったら、権利あるチームが挑戦していこうという事になっていた。
それに、まだ、大会は第一回大会が行われただけだ。
まだ見ぬ強者が参加すらしていない。
虚無六界のまだ、ほんの一部しか、この大会には参加していないのだ。
大会活動を続けて行く内にどんどん、埋もれていた強者達が参加して行くだろう。
第二回、第三回と回を重ねる毎にもっと上のレベルの強者達も参加していくに違いないのだ。
それだけ、第一回大会はお祭り騒ぎのように盛り上がった。
俺も参加する――
私も加わる――
という者が続出している。
第一回大会はそんな状態で締めくくられた。
そして、オフシーズンとなり、ラスティーに運営を任せっきりだった仁義は第二回大会を華芽菜に見せるための準備に取りかかった。
華芽菜達の方もトリッキーズの活躍が台風の目となり、新たな才能がどんどん誕生し、華芽菜のチームが簡単に勝てるような状況ではなくなっていた。
数々の強豪チームが誕生し、大会は盛り上がっていった。
仁義と華芽菜が分かれてからの二年という月日はあっという間に過ぎ去った。
バトル・チアでの練習に明け暮れる華芽菜と鈴子の前に仁義はまたしても突然、現れた。
「よう、かめ子、元気か」
「あんた……」
「ひぃ……あの時の怖い人……」
「お前はたしか、かめ子の金魚のふんの……」
「す、鈴子です。金魚のふんじゃありません」
「そうか、鈴子か。一応覚えておく」
「何とかって大会は上手くいったの?」
怯える鈴子に対して、華芽菜は冷静だ。
度胸も据わっている。
二年前とは違う。
人間的にも華芽菜は成長した。
もう、小娘ではない。
「おうよ、そこでだ。見せ合いっこしようぜ、お前のバトル・チアと俺のプロ・バト。どっちが燃えるかをよ」
「どうやって?」
「ここに、便利なもんがあんだよ。えーと、あれ、どこにしまったっけ……お、あった、これこれ……」
何やら手荷物をごそごそと探し始めた仁義は一冊のノートを取り出した。
「相変わらず、説明無しなのね、あんたは……」
「まあ、良いから、ここの十九ページ目、この迷路を解いてみろよ、ほれっ」
そう言って、ノートを差し出した。
見ると、そのノートには全ページに渡って迷路の様な物が書かれている。
「何なの?この訳のわからないノートは?」
「レコード・ノートってアイテムさ。迷路を解くとその迷路に記された言葉を唱える事によって不可能が一つ可能になる」
「……あんたのやることは何だかいつも怖いのよ。何が起きるか解らないから」
「安心しろ。危険なものじゃない。俺もこの迷路を解いて来た」
「あんたも?」
「そうだ。こいつは俺が所属しているチームのある虚湧界のアイテムだ」
「虚湧界?何よそれ?」
「良いから解け。そうしたら解る」
そう促され渋々、華芽菜は迷路を解いた。
そして、そこに記された言葉――
「え、えーと、これを言うの?恥ずかしいな……ぽ、ぽきゃぷぺらぶへぺらとら……」
と唱えた。
すると――
「え……何これ?」
「え……何これ?」
「か、華芽菜?」
もう一人華芽菜が現れ、元居た華芽菜と同じ反応をする。
鈴子は呆然としている。
何が起きたか解らない。
「よし、金魚のふん、……じゃなくて、とめ子だったか?つる子だったか?お前もやっとけ」
「で、出来る訳ないでしょ……こんな異常事態に……」
「良いからやれよ」
「い、嫌です。絶対に嫌っ」
無理矢理、迷路を解かせようとしている仁義に二人の二人の華芽菜が詰め寄る。
「ちょっとあんた、どういうことよ、説明しなさいよ」
「ちょっとあんた、どういうことよ、説明しなさいよ」
「決まってるだろ、バトル・チアとプロ・バトを見る為だよ」
「はぁ?何言ってんの?」
「はぁ?何言ってんの?」
「バトル・チア見ながらプロ・バトは見れねぇだろうが。同時に見るには完全コピーでもう一つ身体を作らねぇと無理だろうが」
「な……」
「な……」
「俺の方はバトル・チアを見に来た。もう一人の俺はプロ・バトの会場で待ってる。かたっぽは俺に今のバトル・チアを紹介しろ。もうかたっぽはプロ・バトの会場まで俺が飛ばしてやる。どっちがどっちに行くか決めろ」
「どどど、どっちって……」
「どどど、どっちって……」
「あぁ、じれってぇ、お前だ、お前が行け」
せっかちな仁義は片方の華芽菜の腕を掴み、そのまま、異空間の扉を開いてそこに放り込んだ。
そして、嫌がる鈴子にも強制暗示によって無理矢理迷路を解かせ、複製体を作らせて片方を異空間の扉に放り込んだ。
残った方の華芽菜と鈴子は呆然とする。
「無茶苦茶だ。この人やっぱり無茶苦茶だ」
「何てことするのよ」
「何だお前ら、お前らの方が行きたかったのか、向こうに?」
「い、嫌よ、絶対に嫌よ」
「助けておかあさぁ~ん」
何を動揺しているんだという表情の仁義とは対称的に抱き合って怯える華芽菜と鈴子。
この辺りが、人間の世界で普通に生きて来た女の子と非常識は当たり前の世界で生きてきた男子の価値観の違いだった。
「安心しろ。感覚は共鳴している。向こうの感情もこっちに入ってくるさ。じゃねぇと比べられねぇからな」
何処が安心しろなのか解らない二人は――
「ほんと、何しに来たのよあんたはぁ~」
「私の半分帰してぇ~」
と泣き叫んだ。
こうして、華芽菜と鈴子は、現実世界のイベントと非現実世界のイベントを同時進行で体感していくという奇妙な体験をする事になったのだった。
「さぁ、早く俺に説明しろ」
仁義は二人の少女を引きずってバトル・チアの練習場を後にした。
一方、虚無六界とリンクされた虚構世界へと飛ばされた方の華芽菜と鈴子の前にもやっぱり、仁義が待っていた。
「おう、よく、来たな。待ってたぞ」
「ぎゃーっ」
「こっちにもいたーっ」
こちらの非常識世界の華芽菜と鈴子も悲鳴を上げるのだった。
続く。
登場キャラクター説明
001 柳宮寺 仁義(りゅうぐうじ じんぎ)

本編の主人公。
ファーブラ・フィクタの主人公、芦柄 吟侍(あしがら ぎんじ)が怪物ファーブラ・フィクタの七つの魂の一つの転生した魂であるのに対し、彼は七つの内、三つの魂が転生した姿でもある。
神話の時代に存在した168あった核の内、30核分の力を持つ。
プロルパートとも呼ばれる。
人望が厚く、彼を慕う者は多く現れるが、群れるのを嫌うため、単独行動が多い。
悪さをする本人よりもそれを煽る人間達を強く毛嫌いする。
また、必要以上に気に入らない者をいたぶる癖もある。
怒らせたら手に負えない。
ブラッと訪れたある星で、バトル・チアというスポーツと華芽菜という少女に出会い、心に変化が現れる。
002 大和 技陣(やまと ぎじん)

ファーブラ・フィクタの主人公、芦柄 吟侍(あしがら ぎんじ)が怪物ファーブラ・フィクタの七つの魂の一つの転生した魂であるのに対し、彼は七つの内、二つの魂が転生した姿でもある。
右手に5番の化獣(ばけもの)ルルボア、左手に11番の化獣レーヌプスを同時に宿す猛者でもある。
仁義、技陣、時銀の中では最も残忍な性格をしていて、敵に対する容赦は全くなく、命乞いをしようが何だろうが、さからう者は皆殺しにしている。
仁義一派では仁義に次ぐ№2の実力者で、仁義同様に群れるのを嫌い、単独行動を取ることも多い。
003 丹波 時銀(たんば じぎん)

ファーブラ・フィクタの主人公、芦柄 吟侍(あしがら ぎんじ)が怪物ファーブラ・フィクタの七つの魂の一つが転生した魂であるのに対して彼も同じく、七つの魂の内、一つが転生した姿でもある。
仁義一派では№1の仁義と№2の技陣が群れるのを嫌うため、№3である彼がチームを仕切っている。
そのため、彼がリーダーだと勘違いされている。
3番の化獣ウィルウプス・アクルスを宿している。
最強の化獣である13番のクアンスティータとは単なる化獣の名前ではなく、決して解き放ってはならない三つの名前、リステミュウム、レアク・デ、そしてテレメ・デをオブラートに包み込んだ存在でもあると暴露する。
人間の身であるにもかかわらず、神の最強戦力の一角、1級天上使メメタトロンの力を完全に封じ込めるという実力を示した。
004 1級天上使メメタトロン
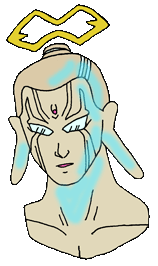
神の使いとして、危険人物、丹波 時銀の抹殺を命じられ刺客として現れるも、3番の化獣ウィルウプス・アクルスの力により完全に動きを封じられる。
力としては、主である神御(かみ)の力を遙かに凌駕する。
崇拝する神御を時銀により虚仮にされ激怒するも、その話しで出てきたクアンスティータという単語の奥にある三つの言葉、リステミュウム、レアク・デ、テレメ・デに言い知れぬ恐怖心を抱く。
005 竜乃宮 華芽菜(りゅうのみや かめな)
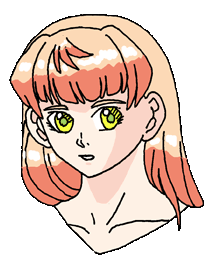
仁義が出会った普通の少女。
バトル・チアというスポーツの女子の部では向かうところ敵無しの有力選手だったが、ルールもろくに知らなかった仁義により、プライドを傷つけられ反発する。
その後、自分を見つめ直し、改めて精進し、仁義のライバルと認められるようになる。
彼女のバトル・チアと仁義の考えたプロフェッショナル・バトル・ストロンゲスト(プロ・バト)とでおもしろさを競うことになる。
不思議な世界には全く、免疫が無く、仁義が強引に押しつける人外の考え方やアイテム等に親友の鈴子と共に翻弄される。
006 榊 鈴子(さかき すずこ)
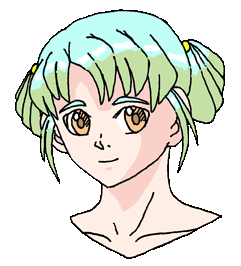
仁義が出会った普通の少女。
バトル・チアというスポーツの世界においては華芽菜と並ぶ有望選手でもある。
ただ、気の強い華芽菜の方がどうしても目立ってしまうため、仁義に金魚のふん扱いを受ける。
仁義の事を初めて会った時から怖い人として認識している。
なるべく逆らわないようにしていたが、強引な仁義の手によって、不思議なアイテム、レコード・ノートの迷路の一つを解かされ、無理矢理身体と心を二つにされてしまう。
その後、バトル・チアとプロ・バトの二つを比べるために身体の一つが華芽菜と共に異世界へと飛ばされる事になる。
007 沢宮 理路(さわみや りろ)

仁義が華芽菜に対抗する為に、才能を買われスカウトされた少女。
元々、天才的プレイヤーだったが、才能のない者達が結託して、彼女とのチームプレーを拒絶したため、孤立状態にあった。
バトル・チアはチームプレーのスポーツだからと我慢していたが、顧問の教師もイジメグループとグルだったと知り、自殺を図ろうと死に場所を探していた時、仁義に引き留められ、退学を決意させられ、そのまま、新チーム、トリッキーズのキャプテンになる。
仁義の考えた、今までのルールに無い方法を多く取り入れ、大会の台風の目となる。
その後、数々の強豪チームが出来る先駆けとなった少女。
008 杉浦 可奈(すぎうら かな)
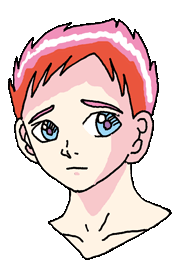
仁義が華芽菜に対抗する為に、スカウトされた少女。
元々はやさぐれた不良少女だったが、仁義に無理矢理喧嘩をふられ、完膚無きまで叩きのめされる。
命が惜しかったら、バトル・チアをやれと脅されそのままトリッキーズのメンバーに。
が、ナイフの様に、ことある毎に、回りに喧嘩を売っていた元の性格は成りを潜め、気弱な性格になってしまった。
009 ぽち子
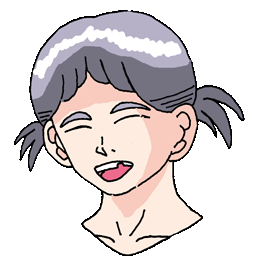
元々は名前すら無かったホームレスの少女。
運動神経を仁義に認められ、三食昼寝付きで、トリッキーズにスカウトした。
仁義の事は夢と希望と食べ物をくれたご主人様と思っている。
ぽち子は仁義が適当につけた名前だが、気に入ってそのまま使っている。